 |
 |
 |
     |
 |
 |
 |
 |
|
 |
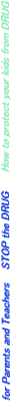
|
 |
 |
 |
     |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
     |
 |
|

大久保圭策
狩山 博文
|
 |
「ダメ!絶対」が崩れたら
〜青少年の薬物対策における初期対応の重要性 |
|
|
 |
|
|
大久保クリニック
大久保 圭策 |
|
|
 |
|
|
ある日、高校二年生のY君のお母さんは、Y君の部屋を掃除していてベッドのマットレスの下から見慣れない錠剤のシートを見つけた。調べると向精神薬とあった。睡眠誘導剤と中枢神経刺激剤。帰宅したY君に問いただしたところ、「友達からもらった」と言ったきり部屋に閉じこもってしまった。父親に話したが、頭ごなしに怒鳴りつけただけで事態はなんの進展もない。お母さんはあちこちの相談機関に相談を持ち込んだ。しかし、あちこちをたらい回しのようにされたあげく、たどり着いた答えは、「本人が何とかしようと思うまではどうしようもない」であった。お母さんは途方に暮れてしまう。そして、後にY君は、「スピード」にまで手を出してしまうことになる。
「本人が何とかしようと思うまでどうしようもない」というのは、たしかに依存症治療の常識ではある。しかし、多くの青少年の違法薬物の使用は、依存症の問題ではない。むしろほとんどの場合は、その前の段階にある。だからといって問題として扱いやすいかというと必ずしもそうとは言えない。そして、青少年の薬物問題で現在最も重要なのは、このグレーゾーンにいる青少年を対象にした薬物対策である。
グレーゾーンというのは、このY君がいまいるところである。つまり、このY君や母親に、この時点で有効な援助ができるかどうかが重要なのである。
「乱用できない社会」から「乱用しない選択をする社会」へ
平成11年5月に「薬物乱用防止五か年戦略」(薬物乱用対策推進本部)が発表された。その中で、基本目標の最初に掲げられているのは、「中・高校生を中心に薬物乱用の危険性を啓発し、青少年の薬物乱用を阻止する」である。「薬物使用は個人の自由と回答する高校生が2割前後」という総務庁の行ったアンケート調査の結果を重く見て、「中・高校生が街頭で一部の不良来日外国人から「スピード」や「S」と称する覚せい剤を気軽に購入するといったこれまでにない状況」が出現しているという認識に立っている。
日本の青少年の薬物防止対策は、基本的に青少年を薬物に近づけないことであった。覚醒剤取締法施行後、覚醒剤を徹底的に排除する施策が採られ、世界史的にも最悪といわれた戦後の覚醒剤乱用の時代は一挙に幕を閉じる。以後、事実上日本国内での覚醒剤製造は不可能となり、日本にはほとんど覚醒剤が存在しないという時代が長く続いた。まさしく「ダメ!絶対」。天然痘を撲滅したWHOに匹敵する快挙である。
天然痘を引き合いに出したついでに、薬物乱用対策を感染症対策と比べてみよう。感染症に対する戦略は大きく分ければ二通りある。ひとつは、WHOが天然痘を地球上から消滅させてしまったように、病原体を徹底的に排除することである。抗生剤などの薬物療法もこちらの戦略と言えるだろう。もう一つは、宿主側の免疫力を付けて病原体がやってきても発病しない身体にするというやり方だ。体力増強やワクチンの接種がこれに当たる。
この二つの方法は一長一短で、宿主側の免疫をいくら高めても、病原菌だらけの不衛生なところでは感染を免れることは出来まい。かといって、病原体を徹底的に駆逐する方法が、最良の方法かというとそうでもない。下手をすると自然に獲得されるはずの免疫力の低下を招きかねないし、個人が感染症から身を守るための努力がなおざりにされがちである。O−157による感染症の大量発生で、あわてて子どもに手を洗う習慣を身に付けさせた親は少なくないはずだ。
重要なのは、この二つの方法のバランスである。
覚醒剤問題に対する対策も、覚醒剤自体を排除することと同時に、乱用する側の「免疫力」を強化することが重要である。「免疫力」とは、個人が「乱用しない選択」をする力のことである。しかし、幸か不幸か日本ではこれまで覚醒剤の排除の方が効果を上げていたために、青少年に「乱用しない選択」ができる力が備わっているかというとはなはだ心許ないのが現状だ。
最近覚醒剤の徹底排除は事実上困難になってきている。「乱用できない社会」から、しようと思えば「乱用できる社会」が再び出現した。そうなると、むしろ問題の力点は、子どもたちが「乱用しない選択」をできるかということに移行する。
青少年の薬物乱用問題の概要※
第三次乱用期と呼ばれる現在、全国の覚醒剤者数は220万人に上るとも推定されている。ことに中・高校生の増加傾向については、今更言うまでもないだろう。青少年自身の薬物に対する抵抗感・警戒感の希薄化はしばしば指摘されることだが、むしろ親や教師の間に危機感が少ないことの方が気がかりである。
ここで、現在の青少年の覚醒剤乱用問題が偶然の一過的現象ではなく、むしろ時代の必然と考えざるをえないことを確認しておきたい。
これまで日本は欧米の先進国と比較して例外的に青少年の薬物問題の少なかった国だったと言える。それにはいくつかの理由があったと考えられるが、そのことごとくが現在危うくなってきている。
覚醒剤乱用の増加を抑制していた条件とは、まず、アクセシリティー(薬物への近づきやすさ)の低さ。次に、覚醒剤もっていた非常にダーティーでアブナイもの、あるいは「ださい」というイメージ。三つ目に、日本社会全体が工業生産を中心とした、「ものを作る」価値観の中で、現在を享受するという価値観よりも「現在を耐えて将来に備える」という価値観が優勢であったこと。四つ目は、青少年の反社会的行動の監視装置としての学校が有効に機能していたということである。
しかし現在、アクセシビリティーは、覚醒剤の流通経路の変化と通信手段の普及で格段に高くなっていることが知られている。これまで、ほぼ完璧に隔絶されていた覚醒剤が存在するような文化圏と、堅気(かたぎ)の人が住む文化圏は、通信ツールの発達と高度情報化社会の出現によって、文化間の垣根が取り払われてしまった。これまであり得なかったような、普通の子どもがある日突然覚醒剤にアクセスするということが可能になってしまったのだ。
イメージの変化については、呼称の変化と摂取方法の変化がある。「S」「スピード」「ICE」などという、いかにもしゃれた名前は、感性優位の若者にとって仲間に一歩先んじているという優越感をくすぐる効果がある。摂取方法が、気化させて吸飲する「アブリ」という方法やジュースに混ぜて飲用するような方法に変化してきたことも大きい。覚醒剤=注射というイメージが非常に強いだけに、注射でないということで覚醒剤だと知らないうちに乱用しているというケースもある。また、注射という方法に比べて、「アブリ」やジュースに混ぜて飲用する方法は、いかにも危険という旧来の覚醒剤のイメージを変えてしまったと言える。
高度消費社会は、子どもたちの価値観を、現在をまさに今消費するものととらえる「消費的」な価値観へと大きくシフトさせている。そして、将来や社会に対して希望を失った中学・高校の若者にとって、「将来困る」という言葉は急速に説得力を失いつつある。
そして、薬物乱用の問題に限らず、1980年代から続いている少年非行の特徴のひとつは、有徴性を帯びていない少年による非行の増加である。この変化は、これまで学校で行われていた、すでにその兆候のある生徒に対して重点的に行なう非行防止対策の有効性を大きく制限することになった。一方では、学校の閉塞性が問題視され、保護者は生徒個々の個別性に対する配慮を求める。あまつさえ、学校や教師の権威は低下の一途をたどっている。このような二律背反の社会的要請の中で、現在の学校は、青少年の反社会的行動の抑止装置としての役割を持ちにくくなっている。
グレーゾーンは、青少年問題
このような時代の変化をふまえれば、現在の覚醒剤問題はこれまでのような白か黒かを峻別する形の対応ではなく、「機会乱用−短期卒業可能性の問題」※すなわちグレーゾーンにいる青少年への援助が重要になる。なぜなら、青少年の覚醒剤乱用の拡大は、覚醒剤依存症者の増加だけではなく、あるいはそれ以上に、薬物を使用した経験はあるが依存には至っていないグレーゾーンにいる青少年の数の増加を意味しているからだ。つまり、これまでのように覚醒剤乱用者と非乱用者を二項対立的にとらえた、闇雲に絶対ダメという一本調子の対応では、その有効性は疑わしくなる。
機会乱用−短期卒業可能性とは、一過性に覚醒剤を使用しても常習にはいたらず、覚醒剤をいわば「卒業」する青少年の問題である。有機溶剤の乱用は、中学年代で多く見られるものの、その中の大部分は中学卒業と同じ時期に有機溶剤の乱用からも「卒業」することが知られている。万引きやバイク盗などの反社会的行動についても、「卒業」と呼ぶにふさわしい現象が起こることが多い。
この段階では、乱用者の中には薬物に対する両価的な気持ちがまだ強く残っている。常習・嗜癖の方に向かう気持ちと、逆にそこから抜け出したいという気持ちである。しかし、この乱用から抜け出そうという気持ちは具体的な行動に結びつきにくいために、どうしてもそれを具体的な行動に結びつける周囲の援助が必要なのである。
このような、短期卒業可能な子どもの場合、それを犯罪的な行動としてのみ捉えペナルティーを課すという方法では、逆にラベリングによって「卒業」不能な方向へ追い込んでしまうという危険がある。また、依存状態に至っていない子どもに対して、依存症の治療原則を持ち出すのもピントはずれである。
グレーゾーンに対する対策には、依存問題や犯罪としてよりも、これを青少年問題としてとらえる視点が必要である。青少年問題とは、社会に参入しようとする青少年と既存の社会との軋轢が、青少年の側に現れる現象である。だから、青少年問題の解答を彼らを矯めることで見いだそうとする試みは、姑息的な解決しかもたらさない。
「青少年の薬物問題を考える会」※※
現場で実際に青少年の薬物問題を扱っている人たちの間では、この短期卒業可能なグレーゾーンにいる青少年の扱いの重要性が認識されている。青少年の覚醒剤事犯を多く扱っている弁護士の小森榮氏は、最近『ドラッグ社会への挑戦』(丸善ライブラリー)という青少年の薬物問題に関する網羅的な著書を出版したが、その中で薬物依存に至る段階を「好奇心の段階・のめり込みの段階・依存の段階」と三つに分類し、最初の好奇心の段階での周囲の関わりの重要性を指摘している。
そして、小森氏は「青少年の薬物問題を考える会」を結成し、このグレーゾーンにいる青少年への対策を中心に置いたマニュアル「親と教師のための初期対応マニュアル」を作成しようとしている。青少年の薬物問題に関わる各分野に呼びかけ、懸賞付きで公募したものを専門家によって練り上げ完成させる予定だ。
このマニュアルは、青少年の薬物問題に直面する可能性の高い親や教師に、「話し合うきっかけづくり」「有効な話し合いのための手法」「なぜ薬物を使ってはいけないのか、親や教師自身が理解するために」「薬物を使うことの弊害を理解させる方法」などについての具体的なノウハウを提供しようとするものである。
完成したマニュアルは、インターネットを通じて広く一般に公開され、学校や地域の各種団体を通じて普及を図るという。
この計画は、いくつかの点でユニークだと言えるが、何といっても最大の特徴は主体が学校や警察でなく市民だということだろう。
覚醒剤問題は、違法行為でもあるために、学校や警察主体のグレーゾーンに対する対策は、どうしても刑罰や処分と切り離すことが出来ない。その点、「青少年の薬物問題を考える会」の活動は、徹底的に青少年の側に立つ立場を貫くことができる。
新しい「社会」生成的で創造的な活動を
実際に薬物を乱用しかけている若者を前にして、ことの重大性を知るオトナはむしろ言葉をなくす。ありきたりの説得やお説教ならば簡単だし、覚醒剤の怖さを説明することだってできるだろう。現代の閉塞感を嘆き、若者に共感したような訳知りオジサンを演じることだって難しくはない。
しかし、本当に有効な援助となると、簡単ではない。家庭では、子どもの行動に文句を言えない親は増える一方である。学校はといえば、教師と生徒の関係は小学生を1時間教室に座らせて授業をすることすら困難なところまで来ている。これが正しい、これがスタンダードだ、といってしまえばすむような時代ではないのだ。
あたかも学校教育制度や地域での青少年育成システムが未だに有効に働いていること、青少年の薬物乱用問題がその他の青少年問題・学校問題と分離して別個に対策を講じうるかのような錯覚を前提にしているような薬物乱用対策は、絵に描いた餅でしかないだろう。社会的な制度や地域や家庭というシステムが、その根底から危うくなっていること自体が、青少年の薬物乱用問題の背景にはある。そして、薬物問題もその他の青少年問題・学校問題と連動して起こっているのだから。
社会学者ハーシィーは、青少年の逸脱行動の原因を社会とのつながりの弱さで説明している。つまり、社会との結びつきが強い人は逸脱行動に走らず、結びつきの弱い人は逸脱行動に走りやすいというわけだ。そして、この社会的な結びつきを構成するものとして、ハーシィーは4つの要素を上げている。社会に対する愛着、社会に関わっていること、社会に参加していること、そして社会を信頼していること。
子どもたちは、「誰にも迷惑かけてない。おれ個人の問題だからほっといてくれ」という。そして少なくない青少年が、薬物使用を「個人の問題」だと考えてもいる。将来困ることになるという説得も、中毒性精神病が周囲に与える影響も、家族の嘆きも教師の心配も、「個人」の自由を振りかざす彼らには届かないように見える。
しかし、薬物を乱用している若者の言う「個人」という言葉を聞いていると、そこには「社会」との関係を結ぶすべを見失った若者の寂しさゆえのツッパリの響きがある。そうだとすれば、そのこと自体が若者にとっては大きな不幸だ。
彼らの主張する「個人」という言葉は、実に重い問いかけである。我々は、彼らとの間に、新しい「社会」という関係を取り結ばなければならない。青少年問題においては、大人がその問題をどのように扱うのかということ自体が、彼らにとっての「社会」であることを忘れるわけにはいかない。
「青少年の薬物問題を考える会」のような市民の立ち上げる活動が、既存の社会に青少年をいかにして順応させるかという発想を超えて、新しい「社会」と若者の関係を創造するような活動として展開してゆくことを期待したい。
※ 第三次乱用期と呼ばれる覚醒剤問題についての詳細は、本誌1998年2月号に『昨今の青少年の薬物乱用の現状と課題』として問題を整理しておいた。筆者のホームページ上の「薬物依存に関する情報」(http://www.o-clinic.com/)と合わせてご参照いただければ幸いである。
※※ 「親と教師のためのマニュアル」懸賞募集に応募された優秀作品は、小森榮氏のホームページ(http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/)で読むことが出来る。 |
|
|
 |
     |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|

